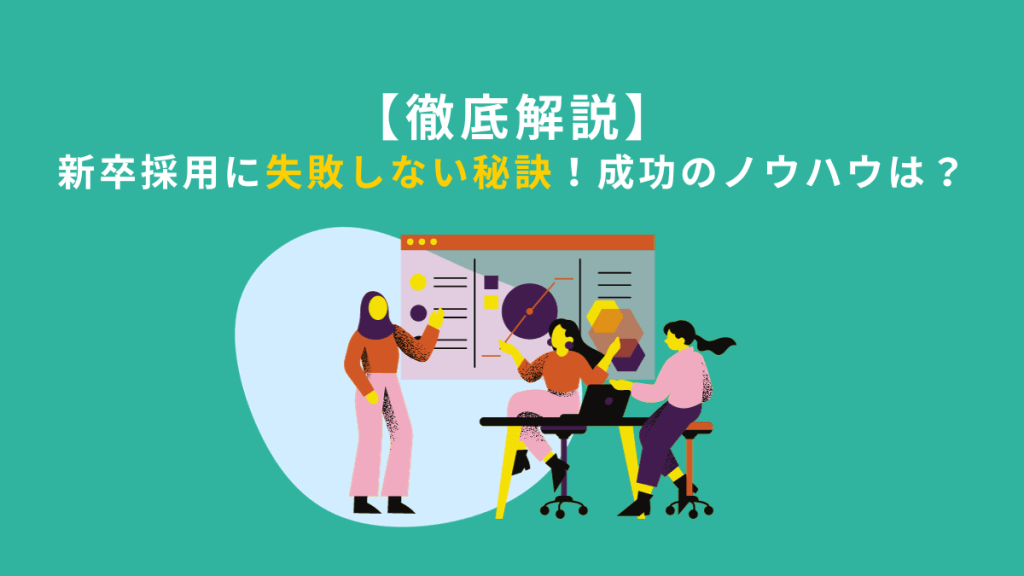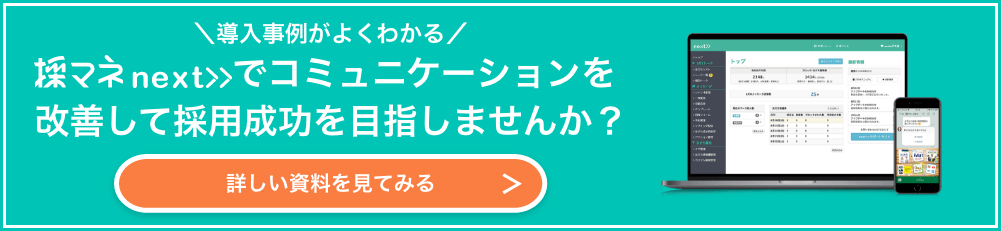新卒を採用したものの、思っていた人材と違ったという声をよく耳にします。採用試験や面接だけでは人物像を把握するのは極めて難しいですが、新卒採用を失敗してしまう企業にはある特徴があります。
この記事では今後、企業の未来を背負う社員となる学生の人物像を見極める秘訣を徹底解説します。
目次
新卒採用に失敗したと思っている理由
新卒採用を失敗したと感じている企業は多く、交流会や面接時の印象と実際に働きだしてからのイメージが違うなどがあります。
実際に、交流会や面接の時だけしか学生とのコミュニケーションをとっていない場合、学生への理解が深まっていないことでギャップを感じます。
学生からしても、実際に入社してみたけれど思っていたような企業とは違うと考えられている可能性もあり、早期退職されることもあります。
また、学生に対する期待度が高いほど、入社後に期待していたほどの活躍がみられないことがあります。
学生は、面接時は採用してもらおうと前向きな姿勢や自己アピールを行いますが、作った人格の可能性があります。
学生はその場で求められている自分を作っている場合、実際はそうではないというケースが見られます。
このように、新卒採用に失敗したと思っている企業は多くあるため、なぜ失敗につながったのかは分析して改善する必要があります。
新卒採用を失敗してしまう企業の特徴は?
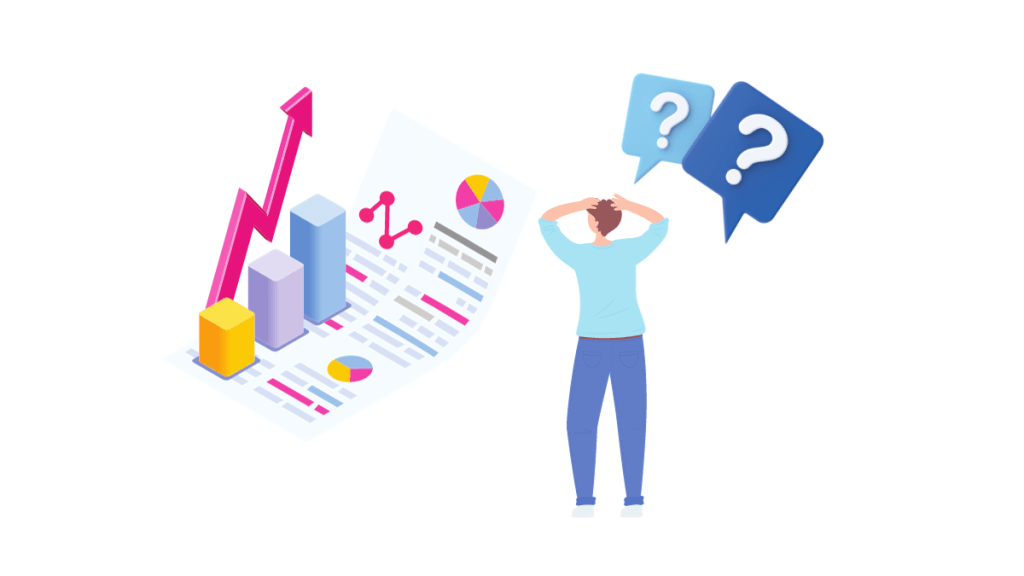
新卒採用を失敗したと感じる企業が多いのに対して、成功したと感じる企業は7割です。
「成功した」と感じる企業と「失敗した」と感じる違いはどこにあるのでしょうか。
ここでは新卒採用に失敗したと感じる企業の特徴を紹介していきます。
特徴1:そもそも新卒採用の募集方法に問題がある
失敗したと感じる企業の多くは、新卒の募集をする方法が不十分であり、求人を出して待っているだけの場合が多々あります。
それでは、求める人材に入社してもらうことはできません。
また、新卒採用のときにPRを積極的に行えない企業ほど失敗することが多いです。
自社の魅力を伝えられていなければ、そもそも学生から応募がこないため、募集方法から見直しをしましょう。
特徴2:レスポンスが遅い
他にも採用スケジュールがスムーズに行われておらず、面接後のレスポンスが遅い企業も失敗をする要因になります。
採用担当者が人手不足で手がいっぱいになっていると、レスポンスが遅くなり、学生の気持ちが離れていくでしょう。
そのため、他社に流れてしまうリスクが高まります。
特徴3:アプローチがうまくできていない
学生へのアプローチ方法に問題がある企業も、採用方法に問題があるといえるでしょう。
企業という組織で働いたことがない学生が描くイメージは現実と異なる部分もあり、学生個々によって適性も違えば性格もさまざまです。
そういった組織に対するギャップをなくすために、自社の社員と交流する場が必要になります。
自社で働いている社員の姿を目に見える形で示し、より正確にイメージをすり合わせることが大切です。
特徴4:採用担当者がいい人材を見極めることが出来ていない
新卒採用の担当者に以下の問題があると人材を見極めることができません。チェックしてみましょう。
・先入観を持っている
運動部だから精神的にタフだなと、色眼鏡で相手を見る。
・自己類似
同じ出身地や趣味が同じであると、それだけでいいイメージを持ってしまい実力以上に評価してしまう。
・ハロー効果
目立っている特徴だけを見ていい印象だけをもってしまい、そこばかり評価してしまいその結果、他の部分までよく見えてしまう。
・中心化傾向
面接時におどおどしていても面接慣れしていないためと思い込み、普通評価で判断をしてしまう。
・対比誤差
前に面接した学生と比べた判断をするため、客観的に評価出来ていない。
上記のように客観的に人を見て判断することができる採用担当者がいないと人材採用に失敗しやすくなります。
採用したものの、こんな人だと思わなかったという結果になりがちです。
自社にあった新卒採用のノウハウ
どの企業も能力が高い人材が欲しいと思うものです。
しかし一般的にいいとされる人材が必ずしも自社にマッチするとは限りません。
求める人物像が不明確なまま、一般的に成績がいい学生、積極性のある学生といったあいまいな基準で採用をしてしまうと失敗するケースが多々見られます。
では自社にあった学生を採用するには何が必要なのでしょうか。
人物像を明確にすることが必要
求める人物像は明確にしてください。「営業を強化したい」「生産性を上げたい」「新しいアイデアをもっと生みたい」など、企業が必要としているものは何かを現場を含めて話し合って明確にしましょう。
面接官は多くて2、3人です。
実際に学生と会い、どういう人物なのかを判断するのは面接官の手腕にかかっているといっても過言ではありません。
今はまだ能力が不十分でも将来の可能性も含め、人を見極める力を強化しましょう。
そのためには、面接官自身に自社の企業理念、今回の採用目的は何か、どんな成果を今後求めるのかを社内で徹底させる必要があります。
求人票の作成、書類選考から採用担当者の仕事は非常に煩雑で、多忙を極めるでしょう。
しかし、忙しい中でこそ簡略化できる部分と人力が必要な部分を見極めて新卒採用に取り組むことが大切です。
学生との接点を増やす
求人広告だけを出している企業だと、学生の目に止まる機会が少ないため、合同説明会へ参加したりインターンシップを開催するなど、学生との接点を増やしましょう。
特に中小企業の場合、大企業や人気の中小企業に比べると認知度が非常に低いため、求人広告だけだと情報が埋もれてしまいます。
また、学生との接点を増やす一環として、人材紹介サービスを利用するのも一つの手です。
自社だけの力で採用活動を行うのが難しいのであれば、紹介サービスの利用は非常に有効といえるでしょう。
内定後や入社後もしっかりフォローを行うことが必要
採用活動の際は積極的に連絡を取っていたが、いざ内定を出してしまうとその後のフォローがおざなりになる企業も少なくありません。
しかし内定後も、この企業で早く働きたいという希望や熱意を維持させることが、入社後のモチベーション維持に大きく影響します。
せっかく採用した人材をどう生かすのかは企業側の接し方次第ともいえます。入社前にインターンシップで職場体験をする機会を設けるのも効果的です。
新人研修などを手厚く行うことはもちろん、話しかけやすい体制作りをするように心がけましょう。
社内での旅行やレクリエーション、飲み会などを企画して仕事以外で仲良くなれる場を提供することで入社後の上下間のコミュニケーションも円滑になります。
採用管理ツールを導入してみる
採用管理ツール「採マネnext≫」であれば、学生との連絡はもちろん、どういう反応があったかなどを一括で管理をすることが可能です。
採マネnext≫をみれば誰でも現状が把握できるので、人事の労務も大幅に削減可能です。
また、学生は従来のようなメールを使用することがなく、LINEを連絡ツールとして使用しています。
文章を考える時間がかかるため、メールでのやりとりに躊躇する学生がほとんどです。その結果、返信をせずに他の企業に流れてしまうことも多々あります。
しかし採マネnext≫ならLINEを使ってコミュニケーションを取れるので、学生は気軽に返信することができるでしょう。
そして返信率が上がり、コミュニケーションが取りやすくなるのです。
細かなコミュニケーションを取ることで学生の本質的な部分を知れるので、本来の人物像を確認することが出来ます。
その他にも「採マネnext≫」の機能は多岐にわたります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
 LINEを使って採用管理を行うべき12の理由【採マネnext≫】
LINEを使って採用管理を行うべき12の理由【採マネnext≫】
まとめ
うちにはなかなかいい人材が入らず、毎年新卒採用に失敗していると感じる方も多いのではないでしょうか。
本当に必要な人材を社内で共有し、採用活動中は学生を細やかにフォローするために採用管理ツールで簡略化できるところを見つけ出すのが近道です。
採マネnext≫は、資料やデモもご用意しておりますので、お悩みの際はぜひご利用ください。