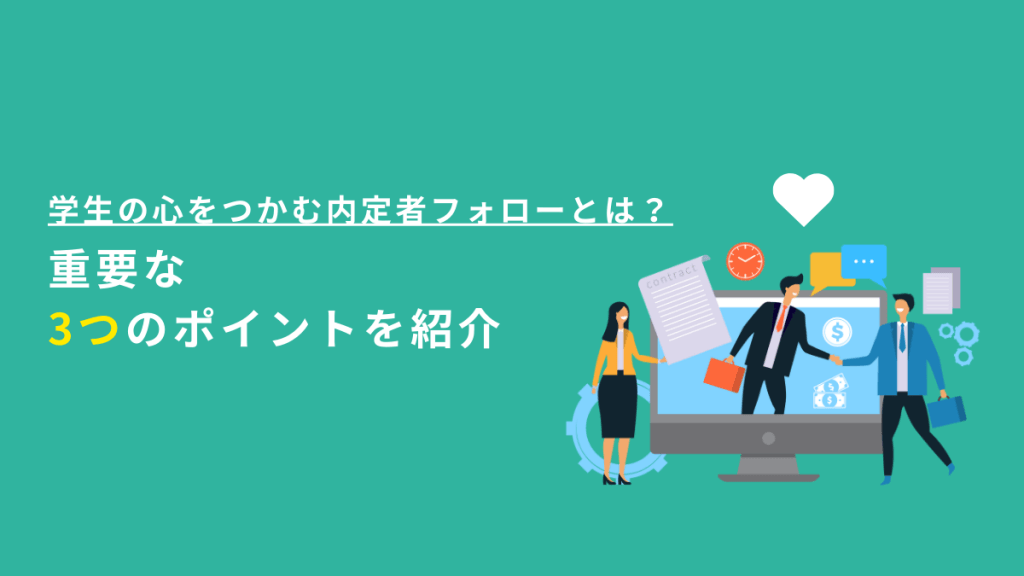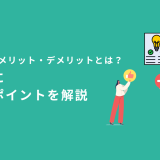企業の採用担当者にとって、学生の内定辞退は大きな課題です。
そのため、内定辞退者を少しでも減らすために、内定者フォローに力を入れるなど、努力している企業もあります。
しかし、十分な内定者フォローを行っているにもかかわらず、あまり効果を実感できない企業も少なくありません。
効果を実践できない場合は、内定者フォローの方法を変えることが必要です。
ここでは、効果的な内定者フォローについて紹介します。
目次
内定者フォローが必要な理由とは
「内定者フォロー」とは、内定者が入社辞退をしないように、企業がさまざまな働きかけを応募者に行うことをいいます。
採用活動は内定を出したあとも続くため、内定者フォローの必要性をしっかり理解しておきましょう。
内定取得者の2人に1人は内定を辞退している
現在、新卒採用はかなりの売り手市場になっています。
学生にとって企業から内定を獲得するのは、以前ほど難しくはありません。
企業が自社に適した人材を確保するのが難しいという状況です。
複数社から内定を得て、その中から入社する企業を選ぶ学生も珍しくありません。
企業が採用する学生を選ぶというよりは、学生が入社する企業を選ぶ時代なのです。
リクルート社の「就職みらい研究所」が発表している、「就職白書2022」によると、前年に比べて内定辞退数が増えている結果となっています。
多くの内定出しをしているものの、内定辞退数が多くなってしまったと、以下のレポートにてまとめられています。
引用:就職みらい研究所「2022年卒の採用活動の振り返り(企業) P10~11」
https://shushokumirai.recruit.co.jp/white_paper_article/20220408001/
学生は内定者フォローを望んでいる
複数の企業から内定を得ても、結局どの企業に入社を決めればいいのか迷う学生も多いです。
入社先企業を決めた後にも、自分の判断が正しかったのか不安になる学生も少なくありません。
学生側は、内定が決まったあとも、内定した企業と接触したいと考えていることがわかります。
せっかく出た内定者の内定辞退にならないためにも、内定後も接触を図り、会社への帰属意識を高めて行くことが重要であることが伺えます。
ミスマッチを減らして入社後の早期離職を防ぐ
内定者フォローは、内定辞退を防ぐことだけが目的ではありません。
入社時点での信頼関係にも繋がるため、結果的に早期離職の防止になるのです。
入社前と入社後で、会社の雰囲気や仕事に対するイメージにギャップを感じると、新入社員は退職を考え始めやすい傾向にあります。
内定者フォローでは学生が不安に感じている部分を事前に把握し、ミスマッチを減らす対処を行いましょう。
内定辞退と同様に、新入社員の早期退職は企業にとって大きな損失です。
内定者のフォローを行なうことで、早期離職を防ぎましょう。
内定辞退を防ぐ!学生が企業を選び続けるポイントとは
内定辞退を防ぐためには、求職者が自社へ応募したときの気持ちを損なわないようにする努力が必要です。
ここでは、内定者フォローで重視すべきポイントを紹介します。
企業に対する魅力
内定者フォローで重視すべきは、常に企業に対する魅力を伝えることです。
応募者に内定を出した後でも、内定辞退が起こる可能性は十分にあります。
度胸試しとして、学生が入社以外の目的で選考を受けている場合もあるため、油断するのは禁物です。
なかには、内定はもらったものの、まだしっかりと自社を理解していないという内定者もいます。
学生は、企業のミッションや将来のビジョン、待遇について知ることで、志望度が高まります。
まだ学生側の気持ちが漠然とした状態であれば、内定者フォローをとおして自社への理解を深めてもらい、「入社したい」と感じてもらえるように働きかけることが大切です。
組織に対する愛着や好感度
企業に対する不安は、内定者の入社意欲にマイナスの影響を与えてしまいます。
内定者フォローをとおして、企業に対する愛着や好感度を育てることが重要です。
そのために、内定者と社員がコミュニケーションをとれる機会を設けることをおすすめします。
経営陣や先輩社員と直接話す場をもつことは、内定者の不安を払拭して信頼感を得るチャンスです。
また、働く自分の姿を具体的にイメージできることで、帰属意識が生まれるかもしれません。
働く会社への愛着や好感度を育てて、入社への期待感を高めてもらいましょう。
マインドシェア
内定者フォローを通して、入社する意欲を失わせないことも必要です。
内定者のマインドシェア、すなわち心を惹きつける工夫をしましょう。
定期的に連絡を取り合い、企業から期待されていることを意識づけると、志望意欲が途切れません。
定期的に内定者に業務に関する課題を出し、提出してもらうのも良い方法です。
学生の心に残る内定者フォロー
内定辞退率を減らすには、学生の心に残る内定者フォローが必要です。
ここからは、企業が行えるフォローには、どのようなものがあるかを解説します。
1.内定者親睦会で食事をする
内定を得た学生の多くは、他の内定者や先輩社員について知りたがっていることが分かります。
そのため、内定者親睦会を開催してみるのがいいでしょう。
内定者同士で顔を合わせて食事をすることで、お互いについて知ることができます。
他の内定者や先輩社員がどんな人たちなのか分かれば安心しますし、企業と内定者の相互理解も深まるかもしれません。
さらに親睦を深めたいなら、社員旅行などに内定者も一緒に連れて行くという方法もあります。
2.内定者研修を実施する
社会人として働くことに不安を抱えている学生も多いことから、内定者研修を実施するようにします。
このとき、研修の中で、先輩社員と一緒に仕事をする機会も設けるといいでしょう。
そうすれば、必然的にコミュニケーションを取る機会もでき、入社後も、スムーズに社内の雰囲気にとけ込めるでしょう。
3.内定者に手紙/メール/LINEでメッセージを送る
内定者に対して、手紙やメールなどコミュニケーションを取る方法も、内定者に安心してもらいやすくなります。
たいていの人は何も音沙汰がないと不安になってしまいます。
しかし、定期的に連絡があれば、それだけで安心できることも多いでしょう。
特にイベントを開催した場合には、欠席者へのアプローチをしっかりと行っておきましょう。
内定を得ていてもイベントを欠席したことで、本当に入社できるのか不安に感じてしまう学生は多いです。
ここで、メールやLINEなどで連絡できれば、就活生の不安は比較的解消されるでしょう。
ただし、連絡を取るときには、手紙やメールよりもLINEの方が望ましいです。
最近の学生は、メールはあまり使用せず、LINEを主な連絡手段として使っています。
メールはほとんどチェックしていなくても、LINEならこまめにチェックして返信する学生も多いです。
この時、LINEを活用する際に注意したい点としては、メールにくらべ管理が煩雑になってしまうことです。
そのため、学生と連絡が取りやすいのはわかっていても、なかなか導入に踏み切れない方も多いのではないでしょうか。
弊社の提供している、採用管理ツールの採マネnext≫では、LINEでの自動応答などの機能や、内定者を選考中の学生と分けて管理する機能などがあります。
採用活動中や内定後にも役に立ち、人事担当者の負担を軽減できて、内定者とのコミュニケーションも捗ります。
4.内定者と社員のメンター制度
既存社員を内定者のメンターにする方法もあり、なるべく若手の社員を選ぶのがいいでしょう。
入社3年目くらいの社員を選ぶことで、内定者との年齢も近く、互いに接しやすくなります。
また、メンターの社員を2〜3年後の自分と重ね合わせてみることができるため、入社後の自分をイメージしやすくなり、エンゲージメントが高まります。
5.早期入社してもらう
大学を卒業するのに必要な単位を既に取り終えている内定者に関しては、早期入社してもらうのもありです。
研修ではなくアルバイトとして雇用する形で働いてもらい、給料を支払うことで、既に会社の一員という立場になってもらいます。
学生にとっては、正式に入社するときには、同期の人よりも一歩リードした状態でスタートできます。
早く入社して即戦力になりたいと考える、やる気のある学生にとっては大きなメリットにもなるでしょう。
まとめ
内定を獲得しても不安を抱えている学生が多いことから、その不安を払拭できるような内定者フォローを行うと効果的です。
内定者同士や既存社員と顔を合わせる機会を設けたり、人事担当者とLINEでやり取りしたりするなどして、入社までに繋がりを維持していきましょう。
弊社の採マネnext≫では、コンサルティングの知識をふんだんに盛り込んだ、採用管理ツールを提供しています。
自動配信できるように情報を登録しておくことで、就活生の選考段階や閲覧している情報に合わせて、最適な情報を自動で届けられます。
資料のご用意からセミナーの開催も行っていますので、ご興味のある方はぜひ、ご相談ください。