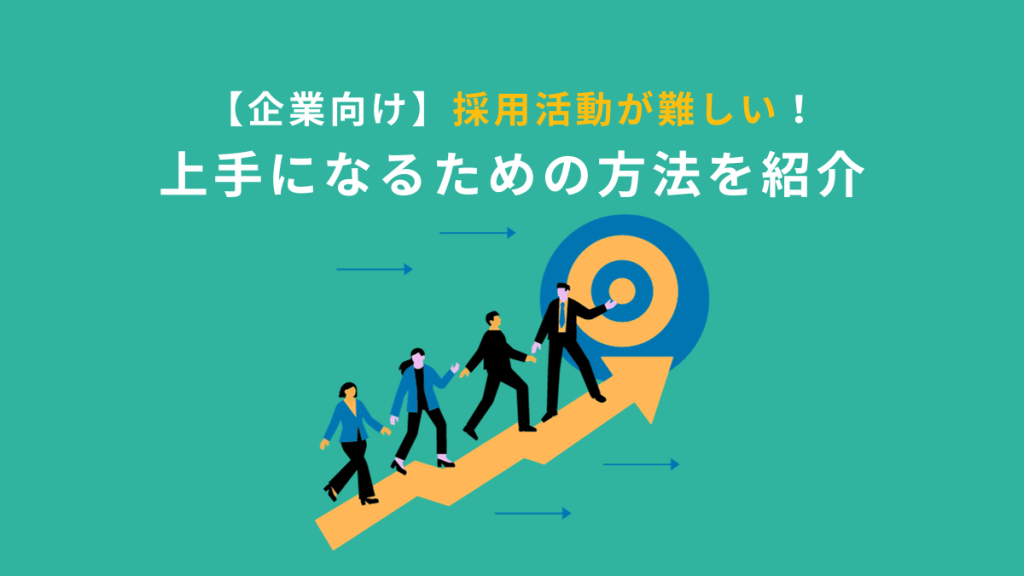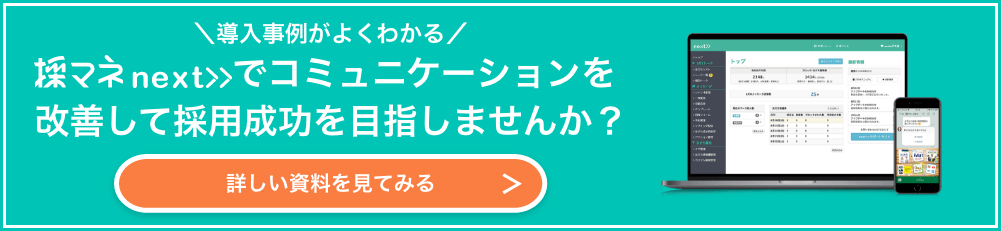求人数の数が求職者よりも上回り、「売り手市場」といわれており、どの企業でも、どこよりも先によい人材を確保したいと考えています。
しかし、思うように人材の確保ができず「採用活動は難しい」と感じている人事担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、採用活動が難しいと思っている企業・人事担当者の方のために「上手に採用活動を行う方法」を紹介します。
目次
採用が難しい理由はなぜ?
採用が難しいと感じる理由は、いくつかあります。ここでは、3つの理由について説明します。
・応募者数が足りない
通常は、求人をした際に応募があった複数の人材の中から人選を行い、採否を決定します。応募者の母数が多ければ「よい人材」を見つけられる可能性も高くなります。
しかし、採用予定人数よりも応募者数が足りていないと、限られた人材の中から人選を行うことになるか、場合によってはひとりも採用できない結果になることもあります。
・応募者のスキルが足りない
企業が求めている人材に対して、応募者のスキルが足りていないケースもあります。人材に対して、何を求めるのかは企業によって違いますが、「最低限持っていてほしいスキル」に満たないと採用にいたらない、もしくは採用した後に早期離職ということもありえます。
・少子高齢化の影響
社会問題となっている少子高齢化の影響で、若い労働力人口が減少しています。加えて、とくに地方では、都会へ就職する若者が多い中、限られたリソースの中から「よい人材を探すのは至難の業」であるといえます。
中小企業で採用が難しい理由
- 知名度が低い
- 競合会社に負けている
- 採用ノウハウが足りていない
中小企業の場合、知名度が低い・競合会社に優位性が負けている・採用ノウハウが足りていないなどの理由で、採用が難しくなっています。
大企業や中小企業でも知名度のある会社は、多くの学生が応募を行いますが、知名度が足りていないとなかなか母集団形成もできません。
他にも、求人を出した際に、競合会社よりも魅力的な福利厚生や勤務体制となっていない場合、比較した際に応募を見送られることもあります。
また、売り手市場の現代では、時代に合わせてより多くの学生の心をつかむための採用活動が行われていないと、人材は多く集まりません。
SNSを活用して企業の知名度を上げたり、戦略的なインターンシップを開催するなど、中小企業の知名度向上のために戦略を練ることが大切です。
採用が上手い企業が行っていることは?
採用が難しい理由を上述しましたが、すべての企業が上手くいっていないわけではありません。なかには、上手くいっている企業もあるのです。
採用が上手い企業が行っていることを見ていきましょう。
採用がうまくいく理由は2つ
・わかりやすい魅力を引き出している
採用活動が上手くいっている企業には、誰が見てもわかりやすい魅力があります。たとえば、「業務内容」や「福利厚生」、また「世の中への貢献度」が明確であると、学生にもそれらの魅力が伝わりやすいのです。
・認知度を上げている
多くの学生や求職者に対して、「コミュニケーションが持てる機会を増やしている」「外部イベントを利用している」など、企業の認知度を上げるための工夫をしています。
たとえば、「コミュニケーションが持てる機会」については、「OBやOGが母校に行き、自社の説明を行わせてもらう時間を持つ」ことが大切です。
「外部イベント」については、「学生向けの就職説明会などに積極的に参画する」など、できることは多数あります。
中小企業には中小企業の戦い方がある!
「自社は、中小企業だから人材が集まらない」と思っている、経営者や採用担当者は少なくありません。
しかし、実際は「やりたい仕事」に着目して、やりがいを重視した場合、大手企業よりも即戦力が認められやすい中小企業に魅力を感じている学生が増えています。
また、福利厚生が充実していることも学生が選ぶ際の指標にもなるので、中小企業でも魅力的なポイントがあれば学生が集まります。
そのため、福利厚生を充実させたり、テレワークを導入したりと、企業の魅力をあげるような改善も重要です。
このとき、SNSを活用してより多くの学生に会社の魅力を拡散して認知度をあげられれば、中小企業でも母集団形成が可能です。
中小企業ならではの戦い方があるため、自社にとってどのような課題があるのか洗い出しを行ったうえで、戦略を練りましょう。
採用上手になるためには?
企業が採用上手になるためには、やはり工夫が必要です。
まずは、どのような人材が欲しいのか、ターゲット像を明確にしましょう。
そして、求人サイトに載せて応募者を待つだけでなく、企業側からターゲットとなる学生にアプローチすることが重要です。
このような「攻めの手法」は、現代の採用活動に浸透しつつあります。
次に、ターゲットの志向性に合わせて自社の魅力と入社メリットを伝えることです。
たとえば、学生が就職先の企業で何を求めているか、「専門的スキルを身に着けたい」「社会貢献の高い事業に関わりたい」といったことが浮き彫りになってきます。
学生の志向性にあった適切なアプローチが、採用成功のカギを握っています。
また、企業社内においての「採用の重要性」と「人材確保の優先順位」を上げることが重要です。
「よい人材を確保」するために、採用部署だけでなく他部署にも協力を仰ぎ、企業全体で「新卒採用」における活動意識を高めていきましょう。
採マネnext≫とは
採用上手な企業になるために、採用管理ツールの「採マネnext≫」をご紹介します。
「採マネnext≫」は、就職活動における学生とのやりとりをLINEですべて行うことができ、学生の情報をデータベース化し、応募から採用までを一元管理できる採用管理ツールです。
メールや電話といった、連絡の取りづらい手法ではなく、学生の中に完全に浸透しているLINEを使うという利点は、すべてのレスポンスを速め、採用を効率化します。
細かなグルーピングができ、メッセージの一斉配信をすることができることも魅力です。
グループ配信だけでなく、1対1トークと自動応答機能で、ライトなコミュニケーションが可能になり、企業と学生の距離を縮めることが可能です。
また、分析機能を使えば、タップ数、外部リンクへのジャンプ数などを可視化することができ、最適なアプローチを導き出すことができます。
まとめ
中小企業が難しいと感じる新卒採用も、多機能な採用管理ツール「採マネnext≫」を導入することで、学生に上手くアプローチしながら管理もスムーズに行えます。
学生を分析して志向性に合った広報活動を行い、新卒採用を成功させましょう。