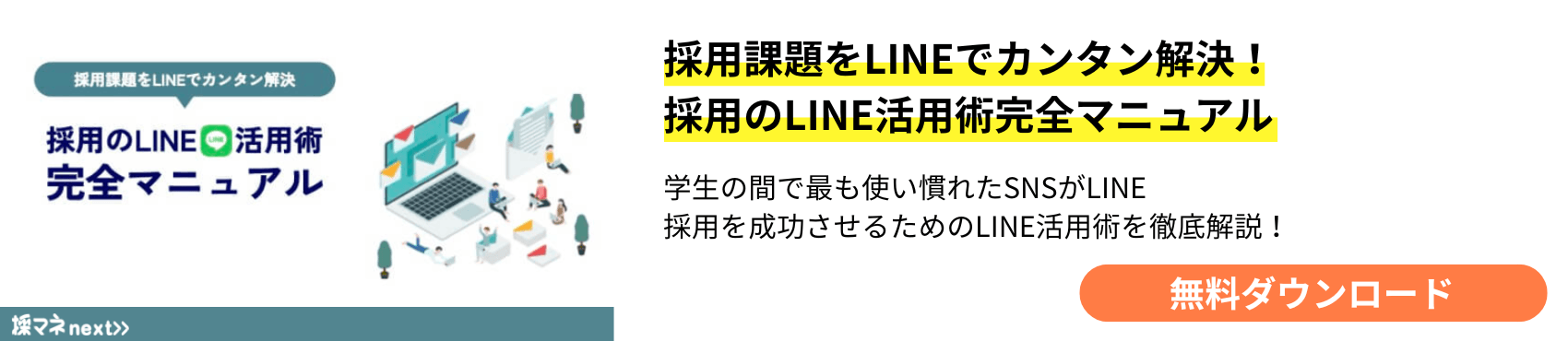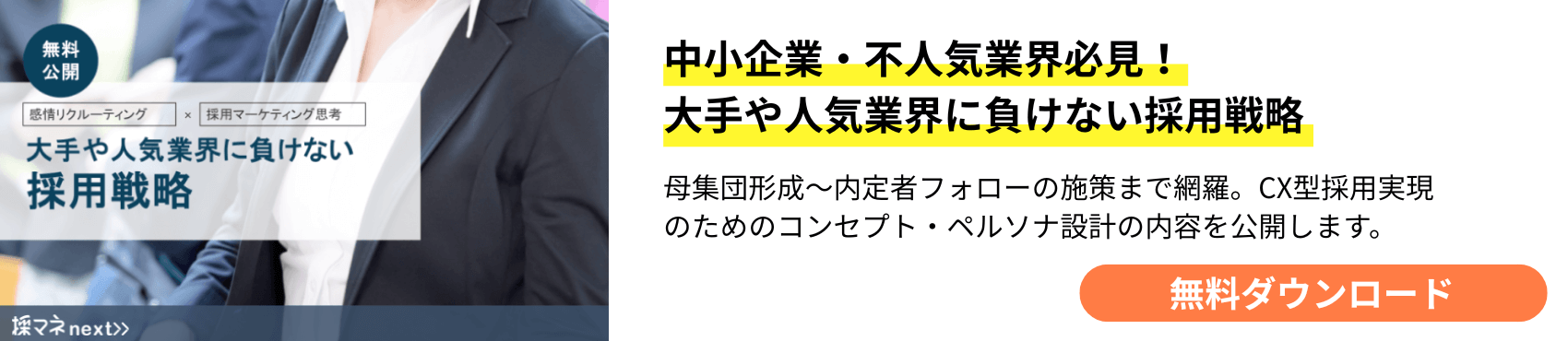「採用活動の中で、選考期間中に応募者から辞退されてしまった」
このような相談をいただくことがあります。
この場合、「選考期間が長い」というのも原因の1つなのかもしれません。
しかし、慎重な選考はどうしても期間は長くなってしまいます。
ここでは、選考期間が長いことのメリット・デメリットと、期間の見直し方について紹介します。
目次
選考期間が長くなることのメリット
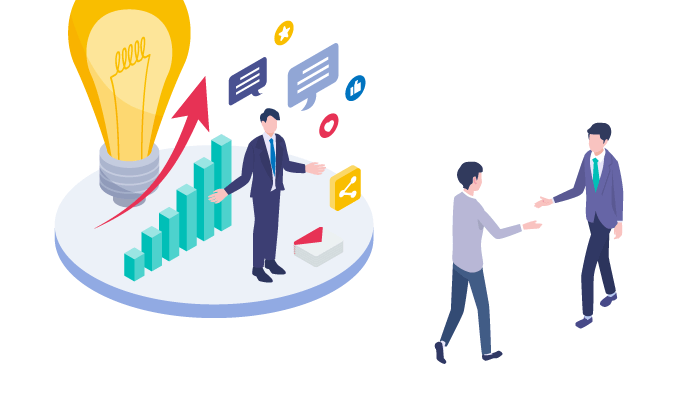
ここでは、採用期間が長くなることのメリットについて解説します。
選考期間が長いという企業は、メリットを上手に活用することをおすすめします。
面接を多く実施できる
選考期間を長くとることができれば、面接を多く実施できます。
面接が1回だけの場合、応募者についてほんの一面しか見ることができません。
面接を複数回実施すれば、応募者のさまざまな面を見ることができます。
1回目の面接で気づかなかった点を、2回目以降の面接で発見できることも多いです。
応募者の見極めがしやすい
面接回数が増えるほど、応募者の見極めがしやすくなります。
面接を1回のみ実施する場合と、2回、3回と実施する場合では結果が大きく変わる可能性が高いです。
応募者側にとっても長いことはメリットとなります。
応募者は採用担当者とコミュニケーションを取る機会が多くなるため、企業に対する理解やイメージが深まります。
多数の面接で、企業と応募者がお互いをよく知ったうえで入社するため、採用後のミスマッチも減り、人材も定着しやすくなるでしょう。
選考期間が長くなることのデメリット

ここでは、採用期間が長くなることのデメリットについて解説します。
選考期間が長いと感じる企業はデメリットを理解して、自社の採用活動に活かしましょう。
他社に流れてしまう可能性がある
応募者は、同時期に複数の会社に応募していることが多いです。
そのため選考期間が長いと、その間に他社から内定を場合に他社を気に入ることがあれば、他社に流れてしまうこともあります。
他社に流れてしまうことを避けるための工夫はもちろん必要です。
さらに他社に流れてしまうことを前提に、多く候補者を集めることは大変おすすめです。これを「母集団形成」とも言います。
母集団形成については以下の記事で解説しています。併せてご覧ください。
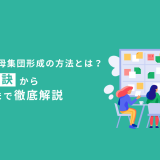 新卒採用の母集団形成の方法とは?成功のポイントから注意点まで徹底解説
新卒採用の母集団形成の方法とは?成功のポイントから注意点まで徹底解説
応募者が不安に感じてしまう
連絡をしない状態が何日も続いてしまうと、応募者が不安に感じることがあります。
応募した後や面接した後は、すぐに連絡が来るものと思っている応募者も少なくありません。
人によっては「落ちたのではないか」「忘れられているのではないか」と不安がよぎります。
合否を通知しないで放置されることで「補欠扱いにされているのではないか」と思われてしまうこともあるので注意が必要です。
- 明確な返答タイミングを事前に掲示
- 定期的なフォロー連絡
これらを実施することで、応募者の不安が軽減されることがあります。
選考期間の長さを見直際に見るべき3つのポイント

もしも、自社の選考期間が1ヶ月を超えてしまうようであれば、期間の見直しが必要です。
長い選考期間を見直す時のポイントは以下の通りです。
・選考フロー
・連絡の早さ
・面接の回数
3回以上面接を実施している場合には、2回程度まで減らしたほうが良いかもしれません。
また、一次面接と二次面接を同じ日に実施するという方法もあります。
これまで、別々の日に3回以上面接をしていた場合などであれば、選考期間を大幅に短縮できるでしょう。
面接自体は複数回実施できて、応募者の負担を軽減できます。
連絡に関しては、求人への応募を確認したら、すぐにレスポンスを返すのが基本です。
当日中の連絡を心がけ、難しい場合には遅くとも翌日には連絡を返すようにしましょう。
・連絡を返すのが遅くなる
・メールでの連絡は時間がかかる、手間がかかる
という方は、LINEを活用した採用活動がおすすめ。
学生の9割以上が利用しているLINEの活用術を知ることで、円滑な選考が可能になります。
弊社ではLINEの活用術をまとめたものを無料で配布しています。ぜひ併せてご覧ください。
選考期間がなかなか短くできない場合の解決策
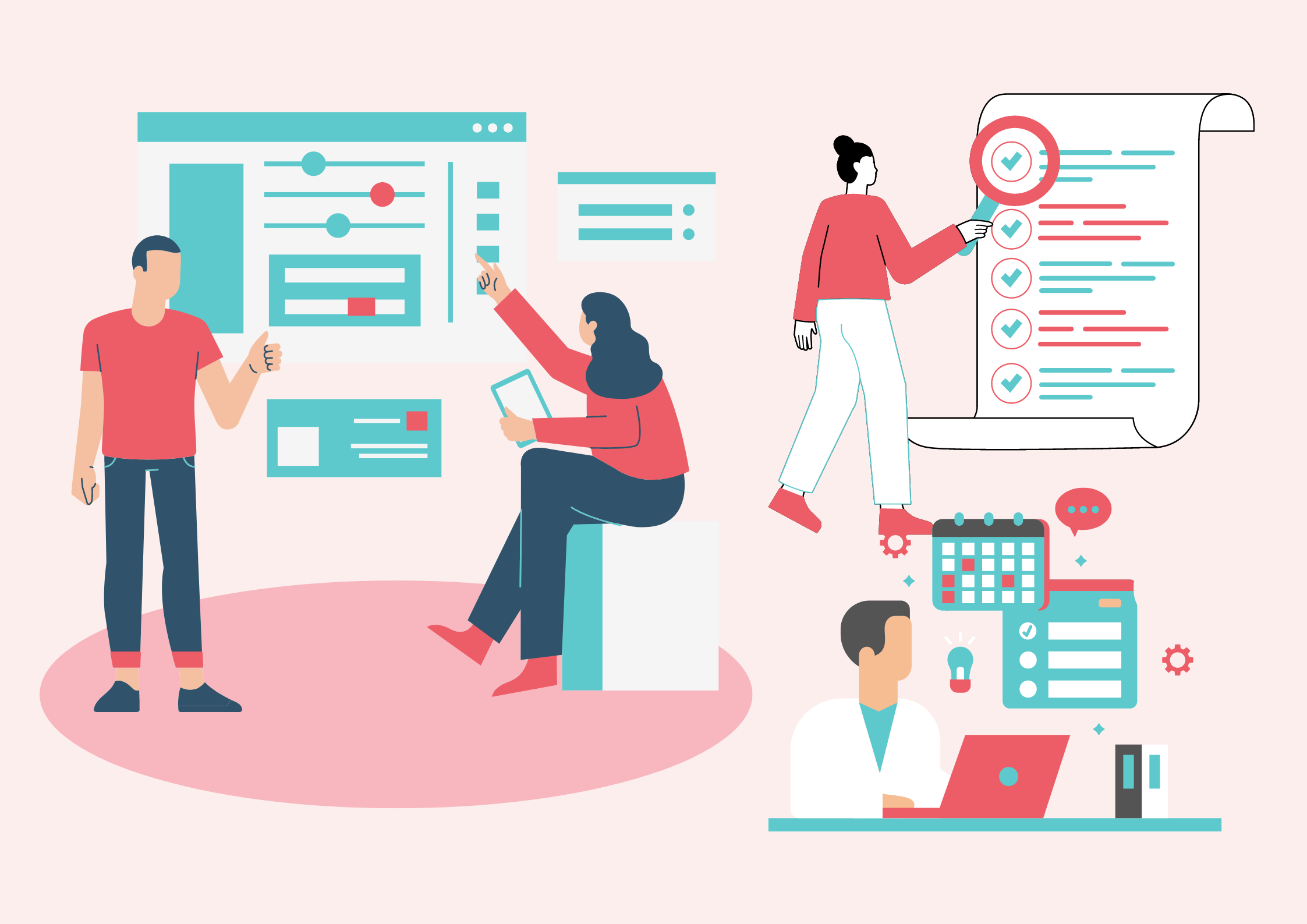
選考期間を見直したとしても、企業によってはあまり短縮できていないこともあります。
慎重な選考を行おうとすると、どうしても日数を要してしまいます。
このような場合、以下のこと検討してみましょう。
実施することで選考期間の短縮につながります。
- 一次面接はオンライン面接を実施する
- 連絡のタイミングを事前に伝える
- 採用管理システムを活用する
一次面接はオンライン面接を実施する
選考期間を短縮したいけど、面接回数を多く実施したいのであれば、一次面接はオンラインで行うことをおすすめします。
オンライン面接は、対面での面接に比べて、労力も時間も軽減できます。
オンライン面接が難しい場合は、1回の面接時間を短くするなどのやり方も良いでしょう。
連絡のタイミングを事前に伝える
次回の連絡のタイミングを応募者に事前に伝えることで、選考結果待ちの不安を払しょくします。
基本的に連絡は素早く行い、遅くなるような時には次にいつ連絡をするのかあらかじめ知らせておくのがおすすめです。
採用管理システムを活用する
応募者への連絡ですが、採用管理システムを活用するのがおすすめです。
データベースとしての機能も充実しているので、応募者のデータ管理も楽に行えます。
また、通知やリマインドなどの機能により、採用担当者の業務量を削減することが可能です。
弊社が提供するLINE採用管理システム「採マネnext≫」もこれらの機能が充実しています。

応募者とLINEによるコミュニケーションが可能なので、柔軟かつ綿密な連絡を取り合うことができます。
どの応募者が現在どこまで選考が続いているかも確認できるので、応募者へのフォローも的確に行なえます。
LINEを活用した採用の成功事例については以下の記事で紹介しています。こちらも併せてご覧ください。
 新卒採用時のLINE活用術を成功事例をもとに徹底解説|メリットも紹介
新卒採用時のLINE活用術を成功事例をもとに徹底解説|メリットも紹介
まとめ

選考期間が長いと、応募者は不安に感じることが多く、途中で他社から内定を得て辞退する応募者もでてきます。
選考が長すぎるようであれば、以下の点をぜひ実施ください。
・面接回数や実施方法などを見直す
・連絡を綿密に行い、応募者の不安や負担を和らげる
(内定辞退防止)
・採用管理システムを活用する
選考の期間については問題ないけど、競合が強くて、なかなか良い人材が取れないという方は、採用戦略を見直すことをおすすめします。
弊社では、採用コンサルタント監修の「大手企業や人気業界に負けない採用戦略」という資料を配布しています。
無料で受け取れるので、ぜひ以下のバナーから受け取ってください。